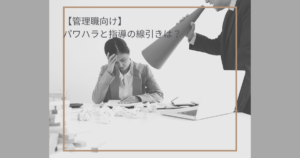職場でパワハラ(パワーハラスメント)を見かけたときに、できること
こんにちは、ハラスメント対策専門家の山藤祐子(ざんとう ゆうこ)です。
あなたは、職場でパワハラを見かけたことはありますか?
パワハラとは
パワーハラスメントの略語。
職場において、地位や人間関係の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて行われる「嫌がらせ」のことです。
厚生労働省では次の3つの要素をすべて満たすものと定義しています。
- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
- 業務の適正な範囲を超えて行われること
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること
「パワハラ」と「指導」の違いは、こちらのページに詳しく記載しました。
https://diamond-c.co.jp/blog/e_2154.html
2020年6月に、パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)が施行され、大企業では職場におけるパワーハラスメントの防止措置が義務付けられました。
2022年4月以降は、中小企業も義務化の対象となっています。
つまり、どんな職場であっても、パワハラを防止する義務があるということです。
だとすれば、見て見ぬふりをしている場合ではないですよね。
働きやすい職場にするためにも、職場からパワハラやいじめをなくすことは、とても大切です。
同僚や後輩がパワハラを受けていた、上司がパワハラをしていた。
こんなときにやってほしいことについて、お伝えします。
※おもにパワハラについてお伝えしていますが、セクハラでも基本は同じです。

1.パワハラ被害者と思われる人に声をかける
相手の意思を確認せず、いきなり「あれはパワハラだ!」と騒ぎ立てるのは、やめておいたほうがいいです。
どんなに正義感にあふれていても、です。
まずは、パワハラ被害者と思われる人に、声をかけてみてください。
「大丈夫ですか?」と、ひとことでも。
そして「私に何か、できることはありますか?」と、聞いてみてもいいでしょう。
同じ職場にいる人は、上司だろうと部下だろうと、みな働く仲間です。
仲間に「私は、見ていましたよ」という意思表示をするだけでも、チカラになれるかもしれません。
関係性にもよるでしょうが、余裕があれば、詳しく話を聞いてみたらいいと思います。
いきなり大きなことをしようとしなくても、声をかけるだけで救われる方がいますから。
あなたにできることを、してみてください。
ただし、なにもしないのは、やめてくださいね。
自分には無理がありそうなら、ほかの人に相談することもできるはずです。

2019年のこと。
小学校の教員が、同僚の教員の目に、激辛カレーをこすりつけるという、ありえないパワハラがニュースに取り上げられたことがありました。
子供たちに「いじめはダメだよ」と教える側でいるはずの教師の間で起こった、執拗な職場いじめ。
なぜ起こってしまったか、ニュースなどでは取り上げられてはいませんが、こうしてパワハラが報道されるたびに、私がいつも思うことがあります。
それは、「誰も見ていなかったのか?」ということです。
周囲の誰かは見ていたはずですし、なにかしらアクションを起こすこともできたはずではないでしょうか。
パワハラや職場いじめが起こる場合、多くのケースで第三者が存在します。
パワハラが加害者と被害者の二人っきりで起こるということは少なく、他の人のいる前で起きるほうが圧倒的多数です。
(反対にセクハラは、多くのケースで加害者と被害者の二人きりのときに起こります)
あなたも、パワハラの現場を見ていたのであれば、ほんの少し勇気を出して、被害者と思われる人に声をかけてみてほしいと思います。
なお、パワハラ加害者に対し「それはパワハラでは?」と進言するのは、かなり高度なことなので、ここでは省略してお伝えしています。
2.パワハラ相談窓口など、しかるべき部署に通報する
会社に、パワハラについて相談できる窓口はあるでしょうか。
またはコンプライアンスに関する相談窓口でもいいでしょう。
そこに、社内でパワハラの疑いがあるということを、パワハラを見かけた第三者として通報してください。
もちろん、被害者と思われる人の意見を聞いたうえで、です(御本人が自分で通報すると言うならおまかせしても)。
あなたの勇気あるたった一言で、パワハラを止められる可能性が生まれます。
ただし、パワハラを見かけた第三者が通報するのは、加害者に処罰を受けてもらうことが目的ではありません。
もちろん、あまりにひどければ、処罰を受けることもあるでしょうが。
この通報は、加害者に「人の目がある」と、知ってもらうだけでもいいんです。
「あ、見られていたんだ」
そう、思ってもらうだけでも、かなり効果はあります。
「人の目がある」と知ることは、パワハラのエスカレートを防げるからです。
加害者にとっては、通報があったと知ることで
「誰かに見られているかもしれないから、気を付けよう」と思い、暴言を吐く歯止めとなりますし、自分の態度を改めるきかっけにもなります。
ハラスメント防止研修の中でも、管理職の方々から
「誰かが聞いていると思うだけで、感情的にならずに済む」
という声をもらうことが、よくあります。
感情的にさえならなければ、言わなくていいことを言わずに済みますし、言わなくていいことを言ってしまって、後悔することもなくなります。
会社で起こることに対して、全てに当事者意識を持ってほしいとは言いません。
でも、どうぞ傍観者にならないで欲しいのです。

パワハラを見て見ぬふりをすることで変化する、周囲の心理状態
私が企業でハラスメント防止研修をするときに、必ず伝えることの一つが、
「ハラスメントを見かけたら、見て見ぬふりをしないでください」です。
こう伝えたときの受講者との会話をご紹介します。

パワハラを見たとしてもハラスメント窓口に通報したり、上司に話すのは、とても勇気が必要です

どうしてですか?

もし通報したら、自分が次の標的になるのではと不安だからです。

自分が通報することで、加害者の人が何か処罰を受けたらどうしようと思うと、なかなか踏み出せません。

確かにひどいことをしてるけど、特定の人だけだし、少なくても私には親切なときもあるし、優しいときもあるんです。

だから、何だか裏切るような気がするので、通報するのは、ちょっと気が引けます。
そうして、通報しない自分を正当化するために、次のように被害者を責める気持ちがでてくるそうなんです。

「よく考えると、〇〇さんも仕事が遅い時があるので、ひどく注意をされても仕方ないかも・・・」
周囲でパワハラを見ている人の心理変化が、よくわかりますよね。
しかし、こんな状態になると、完全に手遅れになっていきます。
パワハラを放置することで、加害者はよりエスカレートし、どうしようもないところまで被害者を追い込んでいきます。
見て見ぬふりをしたことで、さらなる被害を生んでしまいます。
つまり、あなたも間接的なパワハラの加害者となりうるのです。
万が一のことがあれば、あなた自身も心の傷を負いかねません。
いまいちど、良く考えてみてほしいと思います。

パワハラ防止のために、管理職の方に知っておいてほしいこと
パワハラの傍観者にならないためにも、傍観者をつくらないためにも、まずは相談窓口が必要です。
相談する窓口がないと声を挙げることが出来ません。
相談窓口は、設置できていますか?
もし、設置できていたとして、正社員だけではなく、契約社員、アルバイト、派遣社員に至るまで、相談窓口の存在は知られているでしょうか?
パワハラの相談窓口はここにあると、定期的に告知することが必要です。
そして、会社の姿勢として「誰もが相談窓口に安心して相談できる」というメッセージは発信できていますでしょうか。
社員の声は、キャッチできているでしょうか。
いくら通報窓口の体制を整えていても、「何か言ったら、自分が貶められる」と思えば、誰も声を挙げません。

「うちは通報は何もないので、パワハラやセクハラはないと思います」と、コンプライアンス担当の方がおっしゃることがあります。
しかしそれは、残念ながら、通報窓口が運用されていないに等しいということです。
通常、通報窓口が広く社員に告知され、「なんでも言っていい」という空気があれば、パワハラかどうか判断付かないことも含めて、色々と相談が挙がってきます。
要は、社員のパワハラに対する感度が高いということですから。
まだ、パワハラ防止のための対策を講じていない場合は、最優先課題だと認識することが必要です。
どんな対策が必要か迷われる場合には、弊社にぜひご相談ください。
貴社の課題を一緒に考えながら、パワハラ防止研修のカリキュラムをご提案します。
オンライン研修も可能です。
会社からパワハラをなくし、働きやすい環境にしていきましょう。
それが企業の業績アップにもつながるはずです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ハラスメント対策2025年11月26日【ハラスメント防止】これやめて!会社の飲み会でやりがちな行動9点
ハラスメント対策2025年11月26日【ハラスメント防止】これやめて!会社の飲み会でやりがちな行動9点 ハラスメント対策2025年10月28日「ちゃん付け」がセクハラ?職場で「さん付け」が求められる理由
ハラスメント対策2025年10月28日「ちゃん付け」がセクハラ?職場で「さん付け」が求められる理由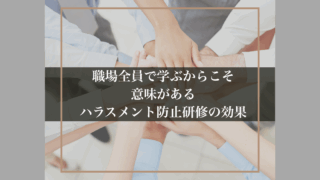 ハラスメント対策2025年8月28日職場全員で学ぶからこそ意味がある ― ハラスメント防止研修の効果
ハラスメント対策2025年8月28日職場全員で学ぶからこそ意味がある ― ハラスメント防止研修の効果 ハラスメント対策2025年7月14日全社員で「ハラスメント防止研修」を受講する重要性とは
ハラスメント対策2025年7月14日全社員で「ハラスメント防止研修」を受講する重要性とは
ハラスメント研修のお問い合わせ・ご相談
平日の日中は、登壇中であることが多いため、電話に出にくい状況です。
メールフォームにてお問い合わせくださいましたら、こちらからご連絡させていただきます。
お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。